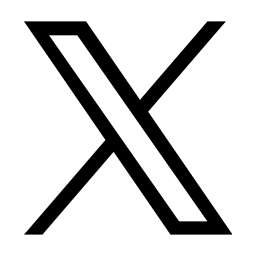副業や転職が当たり前になりつつある近頃、「自宅でネイルサロンを開業したい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
筆者も、まさに「自宅ネイルサロン」を経営しているネイリストの一人です。
では、実際に自宅ネイルサロンを開業する場合、どの程度の資格や準備が必要になるでしょうか。
今回は、自宅でネイルサロンを開業するにあたって、必要な資格や必要な心構えについて私の体験談も含めながら解説していきます!
ネイリストが開業する時に資格は必要?

実はネイリストは、国家資格ではないのです。
そのため、資格なしでも「今日からネイリストになろう」と決めたら、誰もがネイリストと名乗ることができます。
では、実際に自宅ネイルサロンを開業しているネイリストやネイルサロンで働くネイリストは、資格をなにも保有していないのでしょうか。
答えは、NOです。
ネイリストには、資格と同等扱いの「検定」というものがいくつか存在します。
ネイルサロン勤務のネイリストも、自宅ネイルサロン経営のネイリストも、大半のネイリストが、これら検定の級を保有しています。
全くなにも保有していないネイリストより、きちんと勉強してきた証があるネイリストの方が、お客様からの信用度も大きく、また保有している検定級のレベルが自分の技術力を示すツールにもなるため、この検定を受けることを強くおすすめします!
ネイリストの信頼性を高める3つの資格

では、どのような検定があるか、次で具体的に解説していきます。
ネイリストといえば定番の2つの資格と、独立開業をするなら取っておきたい3つの資格を紹介しますね。
ネイリスト技能検定
ネイリストを志す人の大半が、一番最初に合格を目指す検定が、この「ネイリスト技能検定」です。
ネイリスト技能検定は、正しい知識と技術の向上を目的とし、日本のネイル技術に関する検定の中でも最も歴史と実績がある検定です。
ネイリスト技能検定は、3つの級に分かれており、3級から順に受験をしていきます。
・3級=ケア+カラーリング+アート1本
・2級=ケア+カラーリング+リペア+チップラップ
・1級=ケア+リペア+イクステンション+アート
さらに実技に加え、ネイル技術や爪の構造などの知識を必要とする筆記試験があります。
一般的にネイリストの求人には、ネイリスト技能検定2級以上保有という採用条件を設けているネイルサロンが多い印象で、実際に検定を受ける人の半数以上が2級までは続けて受験していきます。
ジェルネイル技能検定
次にメジャーな検定が、「ジェルネイル技能検定」です。
ジェルネイル技能検定は、健全なジェルネイル技術の普及と向上を目的とした、ジェルネイルに特化したネイル検定です。
検定内容は、こちらも同じく、初級・中級・上級の3段階。
・初級:ケア+カラーリング+ジェルカラーリング+ジェルアート
・中級:ケア+カラーリング+ジェルフレンチ・グラデーション・イクステンション
・上級:ジェルイクステンション
初級中級は、筆記試験もあり。
現在は、ジェルネイルが主流なことから、多くのサロンで「ジェルネイル技能検定中級以上」と採用条件を設けているところがあるため、ネイリスト技能検定と併せてジェル技能検定の受験がおすすめです。
ネイルサロン衛生管理士
最後に説明するのは、「ネイルサロン衛生管理士」です。
ネイルサロン衛生管理士という資格は、ネイルサロンの衛生管理の正しい知識をもち、サロン内を清潔に保っていることを示す資格です。
この資格を保有することでJNA日本ネイリスト協会から認定バッジと合格証が届くため、サロン内に掲示しておくことでお客様側の安心材料のひとつになるでしょう。
特に自宅ネイルサロンで独立開業を目指す人には、より多くの方に個人店でも衛生管理をしっかりとしているサロンだと認識され安心して通っていただくために、取得を目指したい資格です♪
あなたに合うのはどれ?ネイルサロン開業の3つの形態

ネイルサロンを開業するにあたり、まず大切なのは自分のライフスタイルや理想の働き方を明確にし、それにあった経営形態を選ぶことです。
店舗の規模や運営方法、開業に至るまでの予算や投資の必要性など、様々な選択肢がある中で「あなたに合うぴったりな形態」はどれなのでしょうか。
一般的なネイルサロン開業の3つの形態と、それぞれの特徴をお伝えします!
賃貸物件での店舗開業
ひとつめは、「賃貸物件での店舗開業」です。
いわゆるテナントを借りて、店舗として使用する開業形態ですね。
【メリット】
・立地を選ぶことができるため、好立地でスタートできて、集客が見込みやすい
・店舗の規模によっては、路面店だけでなく、事業用マンションの一室などもOK
・事業拡大や移転がしやすい(賃貸契約期間終了後に移転が可能)
・内装や設備など自由度を持たせやすい
【デメリット】
・路面店やテナント物件を借りる場合は、初期費用がかさむことも。
・立地や物件によって家賃が高いため、ランニングコストがかかる
・軌道にのるまでの余剰資金が必要
自宅ネイルサロンを開業
次に「自宅ネイルサロンとして開業」をする方法です。
筆者もこれにあたります。
【メリット】
・一般的なテナントを借りるより、初期費用が抑えられる
・ランニングコストを抑えられる
・隙間時間を家事に充てたり、有効活用ができる
・通勤時間がない
・基本的に1人体勢なため、お客様にとってもプライベートな空間を提供できる
【デメリット】
・仕事とプライベートのメリハリをつける必要がある
・生活感を隠す配慮が必要
・駐車場などでご近所にトラブルになる可能性がある
・立地によっては、集客が大変
自宅ネイルサロン開業はこちらの記事で詳しく解説しています!
フランチャイズに加盟する
最後に「フランチャイズに加盟して開業」をする方法です。
フランチャイズ加盟とは、大元の経営母体に加盟し、新しく店舗を出店し、自身で経営していくというスタイルでラーメン屋などでよくある、いわゆる「暖簾分け」という形です。
【メリット】
・母体があるため、お客様から周知されている可能性も高く顧客を獲得しやすい
・店舗の立地がいいことが多い
・しっかりしたフランチャイズ本部であれば、サポートが受けられる
【デメリット】
・初期費用とランニングコストが比較的高い
・ロイヤリティが発生する
・母体と自分のブランドイメージが合っているのか細かく確認をする必要がある
・加盟前に双方でしっかりと契約内容を確認する必要がある
サロンの賠償保険を検討する

ネイルサロンを経営していると、時としてトラブルが発生する可能性もあります。
例えば、
・ネイル施術中にお客様を怪我をさせてしまった
・店舗で火災が発生し、近隣にも飛び火してしまった
・店舗内の椅子が壊れて、お客様が怪我をした
・使用している材料が合わず、お客様がアレルギー反応を起こしてしまった
などです。
このような予期せぬ事態には、保険で備えておくことがおすすめです。
ネイルサロン経営向けの保険としては、
1.施設賠償責任保険(店舗・企業賠償責任保険)
2.製造物責任保険(PL保険)
3.業務遂行賠償責任保険
4.従業員賠償責任保険
5.火災保険
6.休業補償保険
などがあります。
一般的に5の火災保険は、物件を借りる際必ず必要なものですが、1・3・4も加入を検討しましょう。
また、火災やトラブルが原因で営業停止期間が発生したときのためにランニングコストや自身の生活費を確保するために⑥の休業補償保険も加入するのがおすすめです。
ネイルサロン開業にかかる資金は?

ネイルサロンの様々な形態をお伝えしてきましたが、いざ開業するには、実際にどのくらいの資金が必要なのでしょうか。
これから開業を控えている人にとっては、開業資金はとても気になりますよね。
お伝えした経営形態により、開業資金の必要額は大きく異なりますが、目安としてお伝えすると
1.賃貸物件で開業:200万~
2.自宅ネイルサロンで開業:50万~
3.フランチャイズ加盟で開業:200万~
が一般的です。
この開業資金の目安には、物件や設備代に加え、ネイル商材代も含まれています。
サロン開業で役立つ助成金・補助金制度

ネイルサロンを開業する目的に対して、貯蓄をしていく人が多いと思いますが、サロンの規模によっては、より多くの資金が必要な場合もありますよね。
今回は東京都を例に、役立ちそうないくつかの助成金や補助金の制度を少しご紹介します。
(ただし、地域や規模など条件があり、必ずしも全員に適用されるものではないのでご了承ください。)
【創業助成事業】
こちらは、東京都内で創業予定の個人事業主、または創業後5年未満の中小企業者が対象な助成事業です。
賃貸物件の家賃、人件費、広告宣伝費、備品など創業期の支出に対して最長2年間、助成が受けられる場合があります。
(補助率があり、全額ではない)
助成を受けるには、応募後、書類審査や面接審査があります。
【小規模事業者持続化補助金】
従業員を雇う場合、常時使用する従業員が5人以下の小規模事業者に向けた補助金です。
生産性をあげるために購入する設備投資や広告宣伝費などに対して、補助金が出ます。
年に数回の募集があるため、募集情報をチェックしましょう。
【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】
東京都内の商店街で、新事業を開業したい若手・女性の事業者に対しての助成事業です。
店舗の内外装、設備導入などにかかる費用の一部が助成対象。
【IT導入補助金】
中小企業や小規模事業者が、生産性をあげるためにソフトウェアやサービスなどのITツールを導入する際にかかる費用に対する補助金です。
例えば、ネイルサロンなら予約管理システムやレジ関連などが該当します。
助成金や補助金はこちらの記事で詳しく解説しています♪
ネイルサロン開業の流れ

ネイルサロンを開業するには、自分のイメージや理想を形にしていくため、計画から準備、実行、営業開始までいくつものステップが必要です。
とはいえ、どこから手をつけていいか分からない!どこに届けを出せばいいか分からない!という方もいらっしゃいますよね。
一般的に開業をする際は、
- まずは、開業の形態を決める
- 必要資金を確保
- 事業計画書を作る
- 開業日を決める
- 最寄りの税務署に開業届を提出する
- 最寄りの消防局にも届け出をする
- 近隣に挨拶する・宣伝する(広告を出す)
- 開業
- 年に一回必ず確定申告
という流れで進んでいくといいでしょう。
まずは、自身のイメージから開業の形態をしっかりと照らし合わせ、物件選びや商材選び、価格設定等をしましょう。その際役に立つのが事業計画書になります。
そして、開業する際は、必ず最寄りの税務署に開業届を提出しましょう。
書き方は国税庁のWEBサイトに載っているのでチェックしてみてくださいね。
ネイルサロン開業時に重視したいポイント

開業までの流れのほかに、ネイルサロンを開業する際に重視したいポイントをいくつかお伝えします!
サロン勤務で実践的なスキルを習得する
ネイルスクールなどでネイルを学んだ!いざ、開業!ではなく、まずはネイルサロン勤務で実践的なスキルを習得するのが大切です。
ネイリストは、技術職なのでやはり経験がなによりの力になります。
まずは未経験状態を脱するべくサロンワークを経験し、多くのお客様の施術、接客をすること。
サロンの流れをしっかりと身に着けることが大切です。
理想としては、サロン勤務で指名のお客様を獲得し、独立後にそのままついてきていただくことです。
競合店のメニューやコンセプトを調べる
自分のブランドイメージも大切ですが、近隣にある競合店のメニューやコンセプトを把握しておくこともサロン開業時に必要な作業です。
いくら技術売りだとしても、あまりにもメニュー料金に差があり過ぎるとそれだけで客足は遠のいてしまいます。
必ず近づける必要もないですが、競合店の料金形態や対応メニューは調べて、対抗方法を考えましょう。
集客方法をチェック
私が感じた自宅ネイルサロン開業時の最大の難関は、「集客」です。
ゼロからネイルサロンをスタートしようとお考えの方は、この集客方法は必ず決めておきましょう。
集客方法は主に5パターンあります。
- 有料広告(ホットペッパーなど)
- 無料広告(エキテン、ジモティー、ミニモなど)
- SNS(Instagram、HPなど)
- 看板やポスティング
- 口コミ
予算がある方には、反響はもちろん即効性があるのでホットペッパーなどの有料広告が一番おすすめです。
私の場合、転居を機にゼロからのスタート。
さらに子どもが小さく妊娠中の身でランニングコストは抑えたかったため、無料ツールを使い、初めはかなり苦戦しました。
無料のツールから始めたい方は、軌道にのるまでに時間がかかる場合がありますが、固定客がつくと離れにくく、お客様の口コミによっての集客も増えていくので頑張ってくださいね♪
安全管理を重視する
自宅ネイルサロンは、実際に自宅を店舗として使用していきます。
通常ネイルサロンの場合、広告やSNSなどに載せる際には店舗住所を掲載しますよね。
では、自宅ネイルサロンの場合、どうでしょう。
私は小さな子どももいたため、自宅住所を誰でも閲覧可能なネット上に公開することに不安があったので番地以降の住所は非公開で掲載することから始めました。
実際に自宅ネイルサロンを経営している方は、「番地以降の詳しい住所は、ご予約確定時に個別でお知らせします。」と一言添えて非公開にしている方が多いです。
自宅に知らない人を招くことになるので、自宅ネイルサロンを開業する際には、安全面もよく考えて決めていきましょう。
また、お受けするのは女性客のみか、性別を問わないのかも決めておくといいでしょう。
自宅にひとりでお客様対応をしないといけない場合は、なにかあったときの対処法をイメージトレーニングしておくことも大事です♪
ちなみに、雑居ビルの店舗を借りるオーナー1人のサロンや合計2~3名のネイリストが所属する小規模サロンも、やはり安全面は気になるところ。
自宅サロンも小規模サロンも、防犯カメラやセキュリティサービスの導入を検討してみてくださいね。
生活感を排除する
自宅をネイルサロンにする場合、もうひとつ気を付けたいことがあります。
それは、「生活感を出さない」ことです。
お客様は、美容サロンを利用する際にそのサロンの雰囲気で「特別な空間に来ている」気分を味わうことができます。
自宅ネイルサロンとはいっても、生活感があまりに丸出しでは、かえってリラックスできないお客様もいます。
また、小さな子どものいる場合やペットがいる場合も注意が必要です。
自宅から全ての生活感を排除することは難しいため、可能であれば、お客様をお迎えするためだけのネイル部屋を確保しておくことをおすすめします!
また、ペットがいる場合は、アレルギー等あるのでご予約時にその旨を伝えましょう。
そして、どうしても共有部分になってしまう玄関やトイレなども常に清潔を心がけて☆
まとめ
今回は、自宅ネイルサロンを開業するときの必要資格や心構えについて解説しました。
重複しますが、ネイリストには、絶対に必要な資格はありません。
しかしネイリスト技能検定やジェル技能検定は、自分のレベルを証明するひとつのツールになるのでお客様に安心して来ていただくためにも受験することをおすすめします☆
ちなみに私は、リビングにお客様をお迎えしているため、多少の生活感は隠せないままですが、ご予約時に「多少の生活感がある旨」をご説明し、キッチンなどはパーテーションで仕切ったりとできる範囲内での工夫をしています。
また、うちには猫が3匹いるため、今は猫がいることを逆に売りにして、猫アレルギーの方にはご来店をご遠慮いただいています。
生活感やペット問題はデメリットの部分ではありますが、工夫次第では「サロンよりも落ち着く」「猫ちゃんに会いに来ました!」とのお声を頂くことができています♪
これから自宅ネイルサロンを開業する方は、是非工夫をしながら、お客様が安心して任せられるネイリスト、安心して通えるネイルサロンを目指して頑張ってくださいね♪