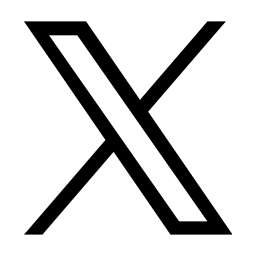現代はネイル文化がすっかり定着していますよね。ネイルサロンの軒数やセルフネイラーの数も増え、誰でも気軽にネイルが楽しめる時代となりました。
そんな中、ネイル文化がいつ頃から誕生したのか気になったことはありませんか?
”爪に色を塗る”という発想は、一体いつから生まれたのでしょうか。
今回は、気になるネイルの歴史を徹底解説していきます。
ネイルについて深掘りをしてみたい人は、ぜひ最後までご覧くださいね。
ネイルの歴史・ネイルはいつからあるの?

世界のネイルの歴史は長く、紀元前3000年以上前に遡るといわれています。
ネイルの技術が日本に本格的に入ってきたのはかなり最近のことですが、「爪に色を塗る」という行為自体は日本的にも世界的にも長い歴史があるのです。
まずは世界的なネイルの歴史から解説してまいります!
古代エジプト時代からネイルはあった
世界のネイルの起源は、なんと古代エジプト時代にまで遡ります。
この時代のミイラの爪を見ると、ネイルのような装飾をした形跡があったそうで、昔のネイルは「ヘナ(ヘンナ)」と呼ばれる植物の花の汁を使って赤色に染められていました。
ヘナと言えば、現代でもヘアカラーで使用されているため、知っている人も多いのではないでしょうか。
このヘナには抗菌作用があるとされ、古代エジプト時代では爪を清潔に保つことを目的とし、性別を問わずネイルを施していたという説もあるようです。
また、古代エジプト時代において「赤色」は、生命や血液などを象徴する”神聖な色”として認識されていました。
階級が高いほど濃い赤を塗り、階級が低い者は薄い赤色しか塗れないというルールもあったそうです。
このように、古代エジプト時代では、爪に施してある色の濃さによって階級を表していました。
マニキュアの発祥は1950年頃のアメリカ

1950年頃に入ると、アメリカでは自動車用ラッカー塗料からヒントを得た「マニキュア」が誕生します。
この頃のアメリカは自動車産業が発展しはじめ、車の塗料技術がどんどん進化していました。
色鮮やかでツヤのある自動車が生産されていく中、それを見た人が”自動車用のラッカー塗料を爪に塗る”ということを思い付いたと言われています。
そして、世界初のネイルポリッシュがアメリカの化粧品メーカー「レブロン」から発売されました。
その後、有名なハリウッド女優たちが指先を美しく彩りはじめ、ファッションの一環としてマニキュアが世界に広がるようになったのです。
日本のネイルの歴史
ここまでは世界のネイルの歴史についてお話してきましたが、日本のネイルの歴史が気になる人も多いのではないでしょうか。
ここからは、日本のネイルの歴史について解説していきます。
日本のネイル文化は飛鳥時代からあった

日本では飛鳥・奈良時代の頃から、”爪に色を塗る”という文化が始まったと言われています。
当時は、赤サビが主成分の「紅殻(べにがら)」を使用して指先に赤色を施していました。
邪気を避けるための呪術として行われていたという説もありますが、額の中央や唇の両端に化粧をしていたこともあり、その延長線で指先に赤色を施していたとも言われています。
平安時代には、階級が高い女性と同じような装いをしていた遊女の影響によって、化粧が下層階級の人々にも広がっていったそうです。
この平安時代では、ホウセンカとホオズキの葉をもみ合わせて爪に色を塗る、「爪紅(つまくれない)」が行われていました。
更に江戸時代に入ると、中国の染色技術に用いられていた紅花の栽培が盛んになり、化粧や爪に使用されるようになります。
紅花で唇を染めることを口紅、爪を赤色に塗ることを爪紅(つまべに)と呼んでいたそうです。
日本のマニキュアの歴史は1960年頃から

終戦後、日本にもマニキュアが輸入されるようになったと言われています。
しかしその頃は、華やかなネイルカラーや光沢感のある爪は、人々にあまり受け入れられなかったそうです。
日本で本格的にマニキュアが受け入れられるようになったのは、1960年頃からだと言われています。
この時代に入ると、日本の化粧品メーカーからも、ピンクや赤のマニキュアが販売されるようになりました。
1960年代には既にファッションも欧米化が進み、指先を華やかにすることへの抵抗感が少なくなっていき、多くの女性が爪のおしゃれを楽しむようになります。
さらに時代が進み、1970年代に入ると定番カラーのピンクや赤の他に、ホワイトやブラウンといったファッショナブルな色味のマニキュアが登場し、ネイルアートの幅が広がるようになりました。
ネイリスト・ネイルサロンの誕生は1980年頃から

1980年代に入ると、日本初のネイルサロンが誕生します。
そして、1985年には日本ネイリスト協会(JNA)が設立され、ネイルとアーティストをもじった「ネイリスト」という造語(職業名)も生まれました。
この時代に入ると、戦後の頃には受け入れられなかったような真っ赤なネイルカラーや、ツヤ感のある華やかなネイルが大流行するようになります。
また、マニキュアでカラーリングをするだけではなく、ラインストーンやアクリル絵の具などを使用したおしゃれなネイルアートが注目されるようになりました。
1990~2000年代はスカルプ・ジェルネイルブームが到来

1990〜2000年代には、スカルプ・ジェルネイルが大ブームになります。
まずは1990年代に、アクリル樹脂を使用した人工爪・スカルプチュアネイルが人気となりました。
ハリウッドで活躍する有名人やモデルたちがスカルプを取り入れたことを切っ掛けに、一般の方にも広まったと言われています。
爪の長さ・形を自由自在に造形できるスカルプは、華やかなネイルアートとの相性も良く、多くの女性から注目を集めました。
さらに2000年代に突入すると、ジェルネイルが登場します。
今やネイルサロンの主流メニューとなったジェルネイルですが、実はまだ25年前後の浅い歴史なのです。
1990年代頃までは、ネイルサロンは価格が高く、”高級”や”贅沢”といったイメージが強く、「芸能人やセレブたちが通う場所」と認識されていました。
しかし、ジェルネイルのブームが加速するにつれて国産の商材が増え、輸入コストが削減されたことにより、施術料金も次第にリーズナブルな価格に変化していったのです。
このように、ジェルネイルの誕生と共に、一般の方が通いやすい価格帯のネイルサロンが増え、多くの方が気軽にネイルを楽しめるようになりました。
2010~現在はセルフジェルネイルも主流に

2000年代にジェルネイルの大ブームが起こり、10年以上経過してもその勢いは止まることなく続いていきました。
ジェルネイルの正しい技術・知識を広めることを目的とした「JNAジェルネイル技能検定」が開催されるようになったのも2010年からです。
そして、2010年〜現在に至るまで、ジェルネイルはその進化を続けてきました。
かつては、UVライトを使用してジェルを硬化させるのが主流でしたが、LEDライトが登場し、よりスピーディーにジェルの施術が行えるようになりました。
商材のクオリティも年々向上しており、拭き取り不要のノンワイプジェルや、攪拌不要のカラージェルなど、画期的なジェル用品が次々登場したことも記憶に新しいところです。
そして近年は、ジェルネイルが登場した2000年代初期と比べると、マグネットネイルやフラッシュネイルといったデザイン性の高いジェルが増え、より多彩なネイルアートが楽しめるようになりました。
さらに、バラエティショップやネットショップなどで本格的なネイル用品が手に入るようになり、セルフネイルを楽しむ方も年々増えています。
まとめ
今回は世界・日本のネイルの歴史や、現在のネイル事情についてお届けしました。
現代はネイル文化がすっかり定着しているため、基本的にはトレンドデザインやセルフネイルの方法に関する情報が多いですよね。
そんな中、少し視点を変えてネイルの歴史を紐解いてみると、これまで以上に関心が高まるのではないでしょうか。
トレンドのネイルデザインは時代と共に変化しますが、古代の人々も指先を彩ることに喜びを感じていたのだと思うと、”変わらないこともある”と感慨深いものがありますね。
現代を生きるネイル女子たちも、自分の好きなネイルデザインをとことん楽しんでいきましょう!