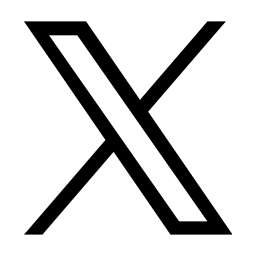キレイなセルフネイルを楽しんでいると、友達から「今度ネイルをつけて」と頼まれたという人もいるのではないでしょうか。
そんな時に一度気にして頂きたいのが「友達からネイル代をもらうか、無料でやってあげるか」という点です。
中には、お金をもらうのは気が引けるという方や、自分はプロじゃないからということで、無料でつけてあげる方も多いようです。
しかし、それを続けていると後々困りごとやトラブルになるかもしれないので気をつけましょう!
今回は、ネイリストとして働いていた筆者の視点から、友達にネイルをする時の料金はいくらが相場なのか、そして無料でやることの懸念点、ネイリストとして働く方の友人料金などもご紹介します。
友達にネイルをする時の注意点

ジェルネイルをセルフで楽しんでいると、お友達から「ジェルネイルをつけてほしい!」とお願いされたことはありませんか?
プロでも、そうじゃなくても、ジェルネイルを塗る技術がある人や、セルフネイルで常にジェルをつけている人は、親しい人から頼まれることがあるようです。
そんな時に一度気にして頂きたいのが、「友達からジェルネイルの料金はもらったほうがいいの?」という点です。
先にお伝えすると、これはその人との関係性や、自分と友人がネイルや施術者をどう考えているかによるので、残念ながら正解はありません。
お互いが納得するなら、100円でも、1,000円でも、無料でも良いのです。
さらに、爪の扱い方やジェルネイルの付け方について、正しい知識がなく、完全に独学でつけている方は、自分以外の人に施術をすると、爪や手指に健康上のトラブルが起こる可能性があります。
自分の爪なら勝手を知るものですが、自分以外の爪はどんな事が起きるかわかりませんよね。
厳しいことを書くようですが、たかが爪でもその人にとって重要な体の一部です。
お友達にネイルを付けて、その爪が病気になってしまったり、状態が悪くなってしまったら・・・考えるだけでも恐ろしいことです。
ネイリストは、爪の状態や爪の病気についても勉強した上で、安全かつ適切な方法でお客さんに施術をしています。
完全に独学で、基本のネイルケアや塗布方法を知らなかったり、爪がどんな状態だとネイルをつけてはいけないのかを知らないという方は、友人であっても他人にネイルをするのは控えることをおすすめします。
一方で、ネイルスクールや通信講座などを使って、習い事としてネイルを始める人も多くなっています。
そこでネイルの基礎知識について勉強したという方は、スクールの相モデルで人にネイルをつけたり、友人にネイルをつけてと頼まれることもあるはずです。
知識や技術を習得した上で実践するのは技術向上に繋がるので、ネイルをつけた方が上手くなるはずです。
では、実際に友人にネイルをする時、自身がネイリストでなくても、お代はもらったほうがいいのかは少し悩みますよね。
実はSNSやネットの口コミでは「代金を貰わないと後々トラブルの元になる」という意見が非常に多いのです。
友達からネイル代はもらう?

一般的にネイルを頼まれた時は、依頼者から「いくらかかる?」と聞かれるケースがほとんどではないでしょうか。
また、ネイル代をお金でやり取りせず、ランチを奢ってもらったり、カフェ代を払ってもらったりと食事や飲み物で対応している人も多いようです。
しかし、そのようなやり取りが事前に何もない場合、「これは無料でやることになっているのかな?」と思ってしまいますよね。
お金の話は言いにくいかもしれませんが、一度塗る前に自分から確認しましょう。
ネイルが終わって以降だと、タイミングが難しくなってしまいます。
ちなみに、ネイリストではなくセルフネイラーである場合、自分以外の人にネイルをしても特に代金は貰わない、無料でつけるという人も少なくありません。
それには以下のような理由があります。
- お金をもらうのは気が引けるから
- 技術に自信がないから
- 時間がかかってしまうから
- 練習台になってほしいから
このように気が引けるというのも頷けるのですが、セルフネイラーの方でも「材料費」と「時間や場所代」を考慮することをおすすめします。
材料費だけもらう
無料でネイルをつけるとして、材料費は考慮していますか?
ジェルネイルに限らず、ネイルをするには材料費がかかります。
ジェルネイルは基本的に「ベースジェル」「カラージェル」「トップジェル」の3つを使って付けていますよね。
付ける前にはエメリーボードで爪の長さや形を整えたり、ルースキューティクルを除去したりといった事前のケアも必要です。
さらに、デザインとしてパーツやシールをつけたり、手描きアートをするなら、その分のネイルパーツやアート用ジェルも必要です。
たとえプチプラでセルフネイラー向けのジェルを使っているとしても、シンプルなクリアネイルだとしても、ネイルをする時は大なり小なり材料費がかかるのです。
そこで、友人からはネイルの施術代としてではなく、材料費として料金をもらうのが良いかもしれません。
材料費を細かく計算するのは難しいので、ある程度の目安を決めて、その範囲内でやり取りをしてみてはいかがでしょうか?
時間や場所代を考える
友人にネイルをする時の、時間と場所はどのようにして確保していますか?
あなたがかなり無理をして時間と場所を確保しているのなら、無料ではなくその時間を確保するための代金をもらったほうが良いです。
例えば小さな子供が居る場合、ネイルをつけている間は子供の様子を見ることができませんよね。
ネイル用品にはアセトンなどの溶剤やニッパーなどの刃物、誤飲してしまいそうな細かい道具が沢山あるので、ネイルを塗っているすぐ近くで子供が過ごすのも危険です。
となると、誰かに子供を見てもらわなくてはなりません。
また、自宅でネイルを塗るスペースが確保できないときは、レンタルスペースを借りる必要も出てきます。
ジェルネイルの施術は、プロでも1時間ほどかかります。
凝ったネイルデザインや、長さ出しをするなら2時間以上かかります。
セルフネイルで自分以外の人にあまり付けたことがないという方は、自分が想像している以上に時間がかかってしまうのではないでしょうか。
その分の時間や場所を確保するのが少しでも大変と思うなら、時間代や場所代だったり、気持ちの分だけでも代金をもらってはいかがでしょうか。
友達料金のネイルはいくらがベスト?

これまで「友人であってもネイル代はもらった方がいい」という話をしてきました。
では、実際に友達料金のネイルはいくらがベストなのでしょうか?
ネイルの平均金額や妥当な金額はよくわからないですよね。
困った時は、以下を参考に考えてみましょう。
材料費は1,000円前後が平均
最もわかりやすいのが、施術料ではなく材料費を負担してもらうケースです。
例えば、シンプルなワンカラーやちょっとしたニュアンスネイルなら500~1,000円ほどが妥当ではないでしょうか。
手持ちのジェルや道具で完結するのであれば、100円でも300円でも良いので、自分が納得する料金を材料費として貰うのがベストです。
10本すべての指にパーツがついていたり、アートの本数が多いデザインを頼まれたら、1,000~2,000円ほどの代金でもおかしくありません。
さらに希望通りのネイルをつけるためにパーツやジェルを買い足しているのなら、パーツ代やジェル代の一部を負担してもらうことも考えましょう。
特に大きなストーンや、1点もののパーツはかなり高額なので、そのことを相手にも理解してもらいたいところです。
時間代や場所代を計算する
セルフネイルなら、自分が休みの日や空いている時間にササッと始められますが、友人にネイルをつけるとなると、お互いの予定を合わせて、時間と場所を確保しなくてはなりません。
ネイルデザインによってかかる時間も変わるので、施術時間に1時間前後かかる場合は1000円、2時間以上かかる時は2000円と決めてしまうのも1つの手です。
また、レンタルスペースやレンタルサロンを借りなくてはならない時は、その場所代を負担してもらうのもよいでしょう。
東京都内を例にあげると、1時間1000円以内で借りられるところから、1時間2000円以上かかるスペースもあり、アクセスの良さや施設の管理状況によって異なります。
食事代やドリンク代を負担してもらう
お金のやり取り自体に気が引ける・・・という方は、食事に行く代金を奢ってもらったり、カフェのコーヒーなどドリンク代を負担してもらうのはいかがでしょうか。
施術前にカフェに行って、ドリンクなどを奢ってもらい持ち帰れば、飲み物を飲みながらネイルを楽しむといったこともできます。
ネイルが終わったらお茶しない?というお誘いや、午前中にネイルをして、ランチに出かけるというのも良さそうです。
金額が妥当かは考えず、直接のお金のやり取りがなければ、気持ちとして楽に過ごせるのではないでしょうか。
ネイリストなら無料・安売りはNG

セルフネイルをしているうちに、ネイリストになりたいと考える人もいます。
筆者もその一人で、セルフネイルを続けているうちに「これを職業にしてみたい!」と思い、スクールに通って、実際にネイリストとして働き始めました。
そして、友人にネイルモデルを自分からお願いする時はお金をもらいませんでしたが、それ以外では通常料金から1割引で施術を受けていました。
プロのネイリストなら、サロンやお店の通常料金から1~2割引くらいまでが参考価格になるのではないでしょうか。
また、ネイルサロンで研修中だったり、研修を終えてネイリストとして働いていると、友人をはじめ親しい人にネイルをすることも増えます。
技術に自信がないと、お金をもらうことがプレッシャーに感じるかもしれませんが、自分がジュニアネイリストであっても、友人同士であっても、代金はもらった上で施術をすることが大切です。
研修中でもお代はもらいましょう
ネイリストはネイルをするのが仕事なので、検定取得のために勉強したり、レッスンやセミナーを受けたり、練習のために時間を費やしたりと、時間もお金もかけています。
ネイリストになってからも、新しいデザインやアートを習得したり、集客、スタッフの働き方、必要経費の計算など、店舗運営にも関わる必要があります。
学ぶこと、やらなくてはならないことは非常に多いのです。
そのような苦労の日々を経て、ネイリストはお客さんから貰う金額分、もしくはそれ以上の価値がある施術をすることが仕事になります。
お金はとてもシビアなものなので、「安かろう悪かろう」という言葉があるように、商品や施術の金額を下げるほど、軽視されたり、大切に扱われなくなるのです。
友人だからと料金を無料にしたり、極端な安売りをするのは、自分自身はもちろん、これまでの知識や経験、技術を安売りしていることになってしまいます。
ネイリストである自分の価値を自分で下げないためにも、施術に対して最低限の料金は貰うことをおすすめします。
もちろん、自分も友人も金額に納得した上で進める必要があり、料金の後出しはNGです。
研修中ならお店のジュニアネイリスト料金でも十分妥当なので、そのことを話してみましょう。
研修を終えてネイリストとして働いているなら、通常料金から1~2割ほど割引したり、サービスでアートやパーツをプラスしてみてはいかがでしょうか。
お金ではなくネイルの面でサービスした方が、お互いに気持ちよく過ごせるかもしれません。
まとめ

友達なら遠慮をしたり、気を使ったりせずに過ごせるものですが、ネイルについてお互いの認識が異なると、残念ながらトラブルの元になってしまうかも。
そもそもネイリストとして働いていても、お客さん一人に対してどのくらいの経費がかかっているかはわかりづらいものです。
セルフネイラーで、ネイルの基本的な知識のある方がお友達にネイルをするなら、まずは数百円でも材料費としてもらいましょう。
自分と相手が納得するなら無料でも良いのですが、時間もかかり場所も必要で、それが何度も続くとなると、負担がかかるのは自分自身です。
そして、ネイリストとして働いているのなら、極端に安売りせず、通常通りの金額や、気持ちの分だけサービスして施術しましょう。
金額の説明をする時は、「仕事としてやっているのに、友達だからって安くしちゃうと通常料金で来ているお客さんに悪いから・・・」と言ったり、「お店としての決まりがあるから・・・」と説明するのが良さそうです。
後悔しないためにも自分なりのボーダーラインを予め作っておけば、お互いに気持ちよく過ごせますよ。