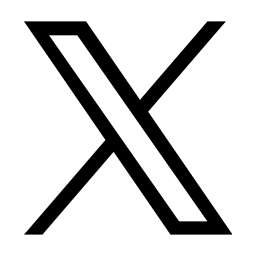近年は市販でも、数多くのセルフネイル向けのアイテムが販売されていますよね。
YouTubeやInstagramなどで、ジェルの技法やアートのやり方が紹介されるようになったこともあり、気軽にセルフネイルを楽しめるようになりました。
しかし、その一方では、間違った方法でのセルフネイルによって、ジェルネイルアレルギーになってしまう方もいるので注意が必要です。
今回は、セルフジェルネイルを安全に楽しむために気をつけたいことや、ジェルネイルアレルギーについて詳しく解説します。
- 「セルフジェルネイルは危険」という噂がある理由
- ・セルフだとグリーンネイルになる可能性が高くなる
- ・自己流のプレパレーションやジェルオフで自爪を薄くする
- ・ジェルネイルアレルギーになりやすい
- そもそもジェルネイルは体に悪いのか?
- ・ジェルネイルが体に悪いと言われる理由
- ジェルネイルを安全に楽しむ方法
- ・ジェルを皮膚につけない
- ・LEDライトを使うようにする
- ・ジェルリムーバー(アセトン)は最小限で使う
- ・適切な頻度で付け替える
- ・正しい方法でジェルオフを行う
- ・正しい方法でプレパレーションを行う
- セルフジェルネイルの主な種類とダメージ対策
- ・一般的なジェルネイル
- ・剥がせる(ピールオフ)ジェルネイル
- 正しい知識とやり方でセルフジェルネイルを安全に楽しもう!
- まとめ
「セルフジェルネイルは危険」という噂がある理由

セルフネイラーさんの中には、「セルフジェルネイルは危険!」「ジェルネイルは体に良くない」といった噂を耳にしたことがある方も多いでしょう。
このような噂を聞くと、「このままセルフジェルネイルを続けても大丈夫なの?」と、不安になってしまいますよね。
しかし、セルフジェルネイルでも、正しい施術を行えば必ずしもトラブルが起こるわけではありません。それではなぜ、セルフジェルネイルが危険と噂されてしまうのでしょうか?
ここではまず、セルフジェルネイルが危険と言われる理由から解説します。
セルフだとグリーンネイルになる可能性が高くなる
ジェルネイルが浮いたままの状態で放置していると、グリーンネイルになる可能性があります。
このことも、ジェルネイルが危険だと言われる理由のひとつです。
グリーンネイルは、緑膿菌という細菌が増殖することで、爪が緑色に変色してしまう感染症のことを言います。
この緑膿菌は、もともと人の体に存在している常在菌ですが、普段はトラブルを招くようなことはありません。
しかし、浮いたジェルネイルの隙間に水が溜まり、湿度が高い状態になると緑膿菌が増殖してしまい、グリーンネイルを引き起こす恐れがあります。
ただ、ジェルネイルアレルギーと同様に、グリーンネイルも全ての方が発症する訳ではありません。
グリーンネイルの場合は、定期的にジェルネイルのメンテナンスを行ったり、浮かない施術を心がけたりすることで、予防できる可能性が高いです。
自己流のプレパレーションやジェルオフで自爪を薄くする

セルフジェルネイルを続けていくうちに、不適切な下準備やジェルオフが原因で、自爪がどんどん薄くなってしまう方がいます。
状態が酷いと爪甲剥離症になる恐れもあるため、「ジェルネイル=爪がボロボロになる」というイメージを持っている方もいるでしょう。
しかし、正しい施術を行えば、そこまで極端に自爪が薄くなることはありません。
近年はサンディング不要のジェルネイルも販売されているため、工夫次第で自爪へのダメージを最小限に抑えることは可能です。
また、ジェルオフの際は削りすぎないように注意したり、オフ後の保湿を徹底したりすれば、自爪が薄くなる・乾燥するといったトラブルを防ぐことができます。
ジェルネイルアレルギーになりやすい
ジェルネイルは、体質や施術の仕方によっては、アレルギーを発症する可能性があります。
セルフネイラーさんだけではなく、プロのネイリストにもアレルギーの症状が出てしまう方がいるため、「ジェルネイルは健康に悪いのでは?」という不安を抱く方も多いでしょう。
おそらく、このような不安感や心配が、ジェルネイル=危険という噂を呼んだ可能性が高いです。
ジェルネイルアレルギーを引き起こす原因は様々で、ジェルに含まれる成分、工程の中で使用するエタノールやアセトン、空気中を舞うダストなどがあります。そして、これらの何に反応しているのかは、個人差があるため一概には言えません。
しかし、継続的にジェルネイルをしている全ての方が、アレルギーになるという訳ではありません。正しい施術を行えば、特に問題なくジェルネイルを続けられる可能性が高いです。
■ジェルネイルアレルギーとは?

「ジェルネイルアレルギー」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような症状が出るのか分からない方もいるのではないでしょうか。
実は、「ジェルネイルアレルギー」は医学的な病名ではありません。
そのため、皮膚科では「接触性皮膚炎」と診断されるケースが多く、これはいわゆる”かぶれ”のことで、皮膚に何らかの物質が触れて炎症を引き起こします。
ジェルに限らず、化粧分や衣類、医薬品、貴金属などが原因で同じような症状になることも。
ジェルネイルアレルギーは、この接触性皮膚炎の一種です。
ジェルネイルが原因の接触性皮膚炎になった場合、一体どのような症状が出るのでしょうか?
ジェルネイルアレルギーについてお伝えしておきます。
・痒みや腫れなどの症状が出る
ジェルネイルアレルギーになると、皮膚に痒みや腫れなどの症状が出ることが多いです。
これらの症状は、ジェルを使用した直後〜数時間後に現れる傾向があると言われています。
そのため、ジェルネイルを施した後、手指に痒みや腫れなどが出た場合は、アレルギーの可能性があるかもしれません。
また、ジェルそのものだけではなく、施術の工程で必要なエタノールや、ジェルオフの際に使用するアセトンによってアレルギーを引き起こしている場合もあります。
いずれにしても、ジェルネイルの施術後に皮膚に異常が出たら、放置せずに皮膚科を受診するようにしましょう。
・1度なってしまうと治らない
ジェルネイルアレルギーは、花粉症や金属アレルギーなどと同様に、1度なってしまうと治すのは難しいと言われています。
のため、ジェルネイルアレルギーにならないように、しっかりと対策を行うことが重要です。
また、アレルギーを発症しているにもかかわらず、そのままジェルネイルを続けると、症状がどんどん悪化してしまう恐れがあるので注意しましょう。
そもそもジェルネイルは体に悪いのか?

ジェルネイルは「体に悪いのでは?」と心配されることがありますが、実際のところは使い方次第です。
ジェルそのものが毒性を持つわけではなく、爪や皮膚に負担がかかるのは施術方法やケア不足が原因になるケースがほとんどです。
たとえば、UVライトの紫外線による日焼けや乾燥、オフに使うアセトンで水分や油分が奪われることは、確かに注意すべきポイントです。
ジェルが浮いたまま放置されればグリーンネイルが起こりやすくなり、無理に剥がしてしまえば爪が薄くなる危険もあります。
さらに、カラージェルやトップジェルの成分が皮膚に触れることでアレルギー反応を発症する人もいます。
こうしたリスクが「ジェルネイルの危険性」として広まっている理由ですが、逆にいえば正しい知識とケアを身につければ多くは防げるものです。
使用する製品の使い方を確認し、オフ後にはオイルやクリームでネイルケアを徹底すればツヤのあるネイルデザインを安心して楽しむことができますよ。
ジェルネイルが体に悪いと言われる理由
ジェルネイルはツヤやデザインの自由度が高く、おしゃれを楽しむための人気アイテムです。
しかしその一方で、「体に悪いのでは?」という声も少なくありません。
実際に施術やオフの方法を誤ると爪や皮膚に負担がかかり、トラブルを招くことがあるからです。
ここからは、具体的にどのような点がリスクとされているのかを解説していきます。
■UVライトによる紫外線の影響
UVライトはジェルを硬化させるために紫外線を照射します。
そのため、使用状況によっては指先の皮膚に日焼けや乾燥を招くリスクがあります。
さらに長期的に繰り返すことでシミや色素沈着といった変化を引き起こす可能性もあり、敏感肌の方ではかゆみや赤みを伴うことも少なくありません。
紫外線は肌内部のコラーゲンにも作用し、ハリの低下や老化を進める要因になると考えられています。
こうした点が「ジェルネイルは体に悪いのでは」と言われる背景につながっているのです。
■アセトンによる肌への刺激
ジェルオフに用いるアセトンは爪や皮膚の油分を一気に取り除く力があるため、乾燥やひび割れになりやすい成分です。
長時間触れていると指先がカサつきやすく、敏感な方では赤みやかゆみが出ることもあります。
コットンとアルミホイルで密閉してアセトンを浸透させる方法は効率的ですが、爪の水分も奪われやすくなり、自爪が薄く弱くなるケースも少なくありません。
こうした状態で無理にファイルを使うと、痛みを伴うトラブルにつながる恐れがあります
■グリーンネイルになりやすい
ジェルネイルをしていると、爪とジェルの間にすき間ができることがあります。
その部分に水分や汚れが入り込むと緑膿菌という細菌が繁殖し、爪が緑色に変色してしまうのがグリーンネイルです。
セルフで施術する場合は、ジェルの密着が不十分だったり浮いた部分を放置したりすることが多く発生リスクが高まります。
特に油分や水分を処理せずにジェルをのせると、浮きやすくなるため注意が必要です。
長期間付け替えをせずに放置することも原因のひとつ。
状況によっては、悪化して痛みを伴う場合もあります。
ジェルネイルの危険性が語られる理由の一部は、こうした感染症にあるのです。
■ジェルを無理矢理剥がして爪が薄くなる
ジェルネイルを無理矢理剥がすと、ジェルと一緒に自爪の表面もはがれてしまいます。
その結果、爪が薄くなり強度が落ちて欠けやすくなるのです。
薄くなった爪は衝撃に耐えられず、先端が割れたり二枚爪になったりしやすくなります。
内部の水分も失われやすくなるため、乾燥や痛みを伴うケースも少なくありません。
本来ジェルオフはファイルで表面を軽く削って、アセトンを浸透させたコットンとアルミホイルで包み込み、時間をかけてジェルを浮かせる処理が必要です。
その工程を省いて一気に剥がしてしまうと、自爪を傷めるリスクが一気に高まります。
ジェルを長く楽しむためには「剥がさないこと」が何より大切です。
もし浮きが気になる場合は必ず正しい方法でオフを行い、仕上げにオイルで保湿をして爪を守りましょう。
ジェルネイルを安全に楽しむ方法

ジェルネイルを施しているからといって、必ずしもアレルギーを発症する訳ではありません。
しかし、アレルギーになる可能性がゼロとは言い切れないため、セルフネイラーさんの中には、不安に感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
そこで、ここからはジェルネイルを安全に楽しむために気をつけたいポイントを解説します。
ジェルを皮膚につけない
ジェルネイルアレルギーを予防するためには、施術の際にジェルを皮膚に付けないようにすることが重要なポイントです。
爪の表面から、ジェルの成分が体内に浸透することはありません。
しかし、皮膚にジェルが付着すると、そこから成分が体内に浸透し、回数を重ねる度に蓄積していく恐れがあります。
これが、ジェルネイルアレルギーを引き起こす大きな原因のひとつです。
特に初心者のセルフネイラーさんは、ブラシワークに慣れていないこともあり、甘皮周りにジェルをはみ出して塗ってしまうことが多いので、気を付ける必要があります。
また、ジェルの塗布量が上手く調節できず、爪の際に流れて皮膚に付いてしまうこともあるので注意しましょう。
LEDライトを使うようにする

ジェルを硬化させるライトにはUVタイプとLEDタイプの2種類があります。
そしてセルフネイルにおすすめなのが「LEDライト」です。
LEDライトは紫外線の照射量が少なく短時間でジェルを硬化できるため、指先の皮膚に与える影響を減らせます。
UVライトでは日焼けや乾燥などの心配がありますが、LEDならリスクを抑えやすいのが大きなメリットです。
また、硬化が早いことでジェルの流れやすい部分も固定しやすく、仕上がりのツヤや密着度が安定します。
最近はセルフ用のキットにもLEDライトがセットになっている商品が多く、簡単に取り入れられるようになっています。
安全性を高めつつおしゃれなネイルデザインを楽しむためにも、ライトの選び方を見直すことはとても大切ですよ。
ジェルリムーバー(アセトン)は最小限で使う
ジェルオフの際に使用する、ジェルリムーバー(アセトン)が原因でアレルギーを引き起こす可能性もあります。
そのため、ジェルリムーバーの量を最小限にして、なるべく皮膚に触れないように工夫しながらオフするようにしましょう。
ただし、オフの際にジェルリムーバーが一切皮膚に触れないようにするのは意外と難しいため、気になる方はネイルサロンでフィルインをオーダーするのもひとつの方法です。
適切な頻度で付け替える
ジェルネイルを短いスパンで頻繁に付け替えると、爪や皮膚に大きな負担がかかる可能性があります。
逆に、長期間ジェルネイルを付けたまま放置すると、グリーンネイルになる恐れもあるため、注意が必要です。
基本的に、ジェルネイルの付け替え周期は約3〜4週間と言われています。
これよりも短いor長い周期でジェルネイルを付け替えることは、おすすめできません。
爪や皮膚の健康をキープしながら、ジェルネイルを続けていくためには、適切な頻度で付け替えを行うことが重要なポイントです。
正しい方法でジェルオフを行う
ジェルネイルを安全に続けるには、正しい方法でのジェルオフが欠かせません。
無理に剥がしてしまうと自爪の表面まで一緒にはがれてしまい、爪が薄くなったり割れやすくなったりします。
これがジェルネイルの危険性としてよく挙げられるポイントです。
本来のオフではファイルで表面を軽く削り、アセトンを染み込ませたコットンを爪にのせてアルミホイルで包んで一定時間置きます。
ジェルが浮いてきたらウッドスティックで優しく取り除き、残った部分は無理をせず再度アセトンで処理します。
こうした工程を守れば、爪への衝撃や痛みを大幅に防げます。
オフの後にはネイルオイルやクリームで十分に保湿し、ネイルケアを徹底することが大切です。
処理を正しく行うことで、自分の爪を守りながら次のネイルも安心して楽しむことができますよ。
正しい方法でプレパレーションを行う
ジェルネイルを長持ちさせて安全に楽しむためには、施術前のプレパレーション(下準備)がとても大切です。
この工程を自己流で済ませてしまうとジェルが密着せずに浮きやすくなり、グリーンネイルや剥がれといったトラブルにつながります。
プレパレーションはまず甘皮処理を丁寧に行い、爪表面の油分や水分を取り除きます。
その後、ファイルで表面を軽く整えてジェルの密着を高めるのが基本です。
処理が不十分だとジェルが先端から取れやすくなり、デザインの持ちも悪くなってしまいます。
正しい方法を守ることでツヤのある仕上がりが続き、爪に余計な衝撃を与えることも減らせますよ。
特にセルフで行う場合は、ネイルキットなどに付属している説明や製品に記載された手順をしっかり確認し、必要な道具をそろえてから取り組むようにしましょう。
丁寧なプレパレーションは、ネイルケアの一部と考えて習慣にするのがおすすめです。
基礎を大切にすれば、指先のおしゃれをより長く快適に楽しむことができますよ。
セルフジェルネイルの主な種類とダメージ対策

セルフジェルネイルにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やオフの仕方が異なります。
代表的なのはアセトンで落とす一般的なジェルと、簡単に剥がせるピールオフタイプの2種類です。
どちらもセルフで楽しみやすい反面、使い方を誤ると爪が薄くなったり乾燥したりとダメージにつながるおそれも。
大切なのは、それぞれのジェルに合った正しいオフ方法やケアを取り入れること。
ここからは、一般的なジェルとピールオフジェルの特徴・そして爪を守るためのダメージ対策について解説していきます。
一般的なジェルネイル
セルフで普及率が高いのは、先ほどからお伝えしている「一般的なジェルネイル」です。
ご存知の通り、ソークオフジェル(ソフトジェル)といわれていて、溶剤(アセトン)で溶かすことができるタイプのものですね。
このジェルについては、先ほどからお伝えしているように
・付け替えの頻度を守る
・オフやプレパレーションは正しい方法で行う
このことに注意しておけば、セルフジェルネイルによる爪のダメージはだいぶ軽減することができます。
剥がせる(ピールオフ)ジェルネイル
セルフネイル初心者にも人気なのが、簡単にオフできる「ピールオフジェルネイル」です。
通常のジェルとは違いアセトンを使わずに自分でペリッと剥がせるのが特徴で、処理が楽という大きなメリットがあります。
利点としては、まずオフの時間を短縮できること。
アルミホイルやコットンを使う必要がなく、ウッドスティックで端から少しずつ剥がすだけで落とせます。
アセトンを使わないため乾燥や痛みといった刺激も少なく、爪や皮膚への負担が軽い点も安心材料です。
100均などでも手軽に手に入る商品が増えており、セルフネイルの入門として挑戦しやすいのも魅力です。
一方でデメリットもあります。
ピールオフは通常のジェルに比べて密着力が弱いため、先端から取れやすい傾向があります。
家事や水仕事が多い方だと数日で浮いてしまうこともあり、持ちの面では十分とは言えません。
また、剥がすときに無理に引っ張ってしまうと、自爪の表面を傷つけるリスクがある点にも注意が必要です。
まとめると、ピールオフジェルは
「短期間だけおしゃれを楽しみたい」
「頻繁にデザインを変更したい」
という方におすすめの製品です。
用途に合わせて通常のジェルと使い分けると、セルフネイルをもっと快適に楽しめますよ。
■ピールオフジェルによるダメージ対策
前述の通り、ピールオフジェルはアセトンを使わず簡単にオフできるのが魅力です。
しかし、扱い方を間違えると自爪を傷める原因になります。
浮いた部分を勢いよく剥がしてしまうと爪の表面まで一緒にはがれてしまい、薄くなったり痛みを感じたりすることがあるので注意しましょう。
ダメージを避けるためには、ウッドスティックを使って端から少しずつ剥がすことが大切です。
急がず丁寧に処理することで、爪への負担を大幅に減らせます。
もし固くて取りにくい場合は、お湯で温めたりオイルをなじませたりすると浮きやすくなり、より安心してオフできます。
ピールオフジェルは持ちが短めなため、長期使用よりも短期間のおしゃれに向いています。
オフした後は必ずオイルやクリームで保湿し、ネイルケアを徹底しましょう。
こうした工夫をすることで、指先を守りながら安心してネイルを楽しめます。
正しい知識とやり方でセルフジェルネイルを安全に楽しもう!

ジェルネイルを安全に楽しむためにも、ジェルを塗布する前の下準備や、ジェルオフを正しい方法で行うことが大切です。
下準備がきちんとできていない状態でジェルを塗布すると、爪の根元や際、中から浮いてしまう可能性があります。
前項でも解説しましたが、ジェルネイルが浮くとグリーンネイルなどのトラブルの原因になるので気を付けてくださいね。
また、ジェルオフの際に表面を削りすぎないように、注意することも重要です。
慣れないうちは、ジェルをどこまで削れば良いか分からず、気がついたら自爪まで一緒に削ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、そのままの状態でジェルを続けていくと、オフの度にどんどん自爪が薄くなってしまうので注意しましょう。
初心者のセルフネイラーさんは、以下の記事で正しい下準備やジェルオフの手順をチェックしてみてくださいね。
まとめ

今回は「セルフジェルネイルが危険」と噂されている理由や、ジェルネイルアレルギーなどについて解説しました。
本記事でもお伝えしてきた通り、基本的にジェルネイルは正しく使用すれば安全に楽しむことができます。
ただし、どんなに気を付けていても、体質や環境などが原因で、ジェルネイルアレルギーや何らかのトラブルを引き起こす可能性がゼロとは言い切れません。
そのため、皮膚に痒みや腫れなどの症状が現れた場合は、早めに皮膚科に行くことをおすすめします。
また、問題なくジェルネイルを施術できている方は、引き続き安全にネイルを楽しめるように、必要な対策をしっかり行うようにしてくださいね。
ジェルネイルアレルギー対応のサロンがある理由|安心してネイルを楽しむためにできること
https://www.nailjoshi.com/26644/